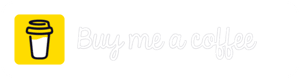コンテンツ作成の「沼」を避けてスピードアップする秘訣
ブログやYouTube、SNSなどで情報発信をしている皆さん、コンテンツ作成中に手が止まってしまい、「沼」にはまって抜け出せなくなった経験はありませんか?
この音声では、コンテンツ作成の沼にはまる原因とその回避策について、非常に重要なヒントが語られています。今回はその内容を要約し、皆さんのコンテンツ作成スピードアップに役立つ考え方をご紹介します。
コンテンツ作成の「沼」とは?なぜハマるのか?
コンテンツ作成は、一度つまずくと作業がなかなか進まなくなってしまうことがあります。これが「沼」です。具体的には、例えば動画のスライドを作成中に、そこで使う情報が「本当に正しいのか?」と疑問に思い、調べ始めたら色々な情報が出てきて混乱してしまい、結局作業が全く進まなくなる、といったケースです。
このような状況は、ブログ記事を書く際に何かを調べ始めたり、使う画像を探すのに30分、1時間とかけてしまったり、といった形でも起こり得ます。無料での情報発信を毎日継続していくためには、この「沼」にはまらないことが非常に大切なのです。
なぜ沼にはまってしまうのでしょうか?一つの大きな原因として、完璧主義な人が陥りやすい問題だと言われています。情報を正確に伝えよう、完璧なものを作ろう、という気持ちが強すぎると、小さな疑問点にも立ち止まってしまい、先に進めなくなってしまうのです。
沼を避けるための「本質を見極める」という考え方
では、どうすればこの沼を避けることができるのでしょうか?音声の中で提案されている重要な考え方は、「本質は何なのか」を常に見極めるということです。
例えば、ある研究結果を引用してコンテンツを作成する場合を考えてみましょう。真面目な人ほど、「1900何年に、どこの大学の誰々教授が、こういう研究を行って、こういう結果が出ました」といった詳細を正確に調べようとします。マーケティングの世界でよく知られる、ジャムの実験(選択肢が多い場合と少ない場合で売れ行きが変わるというもの)が良い例です。この実験についても、「どこの大学の誰がやったか」といった詳細を正確に調べようとすると、沼にはまってしまう可能性があるのです。
しかし、私たちが歴史の授業をしているわけではありません。伝えたい本質は何でしょうか?それは、「こういう研究があって、こういう結果が出た」という研究結果の内容そのものではないでしょうか。大学名や教授名、年号といった固有名詞は、必ずしも重要ではないことが多いのです。海外の大学名などは、有名なところ以外は聞き慣れない場合も多く、覚えていないことすらあります。
「海外の、とあるすごそうな大学の、すごそうな教授が、こういう研究をしたらしい」という大枠が伝われば、多くの場合は十分なのです。もちろん、正確に言えるに越したことはありませんが、調べるのに時間がかかるのであれば、本質である「研究結果の内容」を伝えることを優先する方が、沼にはまらずに済みます。
「正しい」「間違っている」は捉え方次第
さらに、コンテンツ作成で立ち止まってしまう原因の一つに、「この情報は正しいのだろうか?」「間違っていないか?」と悩みすぎるという点があります。しかし、「正しい」「間違っている」という判断は、事実として存在するものを除けば、実は捉え方の問題であることが多いのです。
例えば、「接触頻度が増えれば好感度が上がる」というザイオンス効果のような法則があります。これは確かにそういう面もありますが、嫌いな人に何度も会えば、むしろもっと嫌いになるというケースもあります。つまり、これは「絶対の真理」ではなく、あくまで「そういうケースがある」というものに過ぎません。特定のケースでは正しいけれど、別のケースではそうではない、という情報はこの世にたくさん存在するのです。
また、コンテンツで「ノウハウ」を語る場合も同じです。「このノウハウは合っているのか?」と考える必要はありません。ノウハウとは、あくまで「私はこうやりました」という自身の経験談に過ぎないからです。そのやり方で自分がうまくいったのであれば、それは自分にとっては「正解」なのです。自分と似た状況の人であれば、その人にとっても正解となる可能性は高いでしょう。
マインドセット(考え方)についても同様です。「正しい考え方」「間違った考え方」というものは存在しません。それは「私はこう考えています」という、自分自身の解釈の問題です。
つまり、すでに事実として確定しているもの(例:東京オリンピックは2020年に開催された、など)は間違えると問題ですが、それ以外の捉え方や解釈、ノウハウといった情報には、「絶対的な正しさ」は存在しないことが多いのです。そういった情報について、過度に正確性を追求するために時間をかけすぎる必要はない、と言えるでしょう。
情報の取捨選択と「線引き」の重要性
加えて、情報を受け取る側にとって、情報が多すぎると、それを理解し記憶するのが大変になります。研究結果の詳細な年号、大学名、教授名まで伝えると、覚えなければならない情報が増え、かえって本質的な内容が頭に入りにくくなる可能性もあるのです。ジャムの実験の話は何度も聞いているけれど、どこの大学の誰がやったかは覚えていない、という人も多いはずです。それでも、実験の内容が伝われば良いわけです。
だからこそ、伝えたい本質を見極め、どこまでの情報を伝えるか、どこからを省略するかという「線引き」を明確にすることが、コンテンツ作成のスピードアップには非常に重要になります。すべてを正確に伝えようとするとキリがなくなり、「これで正しいのかな?」と悩み続けて、結局コンテンツが完成しない、ということになりかねません。
まとめ
コンテンツ作成の「沼」にはまらないようにするためには、以下の点が重要です。
- 完璧主義になりすぎず、まずは全体を完成させることを目指す。
- 情報の正確性よりも、「最も伝えたい本質は何なのか」を見極める。
- 事実ではない情報(解釈、ノウハウなど)については、絶対的な正しさを求めすぎない。
- どこまで正確性を追求するか、どこまで情報を省略するかという「線引き」を明確にする。
これらの考え方を実践することで、コンテンツ作成にかかる時間を短縮し、より効率的に情報発信を継続できるようになるはずです。ぜひ意識してみてください。